お前らくっついちゃえよ!浅草に実在する最強のオカルトパチンカーが一人の男の人生を変えるまで!

浅草に一人の女性がいる。名前をバタフライという。もちろん偽名だ。妙齢だが美魔女と言えば美魔女。情に厚く、そしていつもベロベロに酔っている。ネイリングに余念がなく、飼猫二匹とパチンコを愛する人だ。
俺が彼女と知り合ったのはおよそ八年ほど前、浅草のとあるバーでの事だった。
当時俺は足立区から越してきたばかりで近所に友達もおらず、また嫁も彼女も居なかったのでとにかく寂しん坊だった。棲家を変えたばかりの心細さもあってどうにも落ち着かず、感じの良いバーを探すため仕事終わりに夜の街をさまよっていた。
誰の紹介もなく、いちげんの店を渡り歩くのは少々怖くもあったけど楽しくもあった。ただ、思い返してみればあんまし良い思いはしてない。国道沿いの洒落た店では鼻メガネみたいな顔したパーマの店員さんと良く分からん確率論にまつわる話から論争になって嫌な想いをしたり。うっかり入ったお店が思いっきりガチの方のゲイバーだったり。あるいはフラッと立ち寄ったろばた焼き屋がゲイろばた焼き屋だったり。
一ヶ月くらい河岸を変え続けてたどり着いたのが、例のとあるバーだ。当時の俺の家から最も近い店だったので敢えて後回しにしてたのだけども、いよいよピンと来る所がなくなって入ってみる事にした。
木製のチープな扉を押し開く。酒とタバコの香りがした。
カウンターの後ろにはマスターらしき小柄な人物がヨレたパーカーを着て立っていた。外からではよく分からなかったけど、なかなか混んでる。促されるままL字のカウンターの最奥に座ると、まさしくその隣が彼女だった。すでにすっかり出来上がっていて、初対面の俺の個人情報をあけすけにせんと尋ねてくる。最初のビールを飲み終わる前に、家の場所までバレた。
「え、あそこ住んでるの! 近い近い。ウチのうち、あそこのコンビニの──」
彼女の一人称は「ウチ」だった。東京で使う人は珍しいので尋ねてみたところどうやら千葉との事。知的好奇心が湧いたのでタバコを吸いながらスマホで調べてみた所、房総半島の一部でも「ウチ」が一人称の地があるらしい。なるほどなぁ。とひとりで納得しながら頷いていると、バタフライさんがこんな事を言い始めた。
「ちょっとー! マスター! コイツ、あたしのここんトコ触ったゾ!」
誰かがバタフライさんにセクハラしたらしい。酒の席でのうっかりタッチ事件だ。まあ良くあることなんで無視してスマホ見てたら肩を叩かれた。バタフライさんが俺に指を向けている。
「コイツコイツ! あたしのここんトコ! ちょっとー! やめろよテメーもう!」
曰く、俺がバタフライさんの二の腕を触ったらしい。当たり前だけど触ってない。俺の興味は既に房総半島の歴史を調べるフェーズに入っておりスマホに夢中だった。とんだ冤罪である。一瞬身構えるも、周りのお客さんもマスターもまるで気にしていない。繰り返し主張するバタフライさん。やがてカウンターの向こうのマスターがタバコの煙を吐きながらこう返事した。
「へへへ……」
「へへへじゃねェよ! もう……! もう一杯同じのちょうだい」
「アザース!」
「でさー、ウチのうち猫がいるんだけどさぁ。……ええと、あんた名前なんだっけ?」
「あ、ひろしです」
「ひろしィ? ひろしって言うの? ったく! ひろしって名前のやつにはなァ、碌なやつがいねェんだぞ? そォんなヒィロシにだァ~まされェ~」
「(歌い始めた……!)」
「マスター、サザン聴きたくなっちゃった。サザンかけてかけて……! でね、ウチのうちの猫がァ……。そのー、あれ? 名前なんだっけ?」
「ひろしです」
「ひろしって名前はなァ、ホントに碌な奴が……そォんなヒィロシにだァ~まされェ~」
ビールを煽る。もう一度バタフライさんを見て、そしてマスターを見た。すごい。二の腕触られたみたいな話が3秒でどっか行ったし、名前を何回も聞いてくるし、ぶっ壊れたラジオの如く同じフレーズをリフレインする。そして周りの客も一切気に留めてない。なるほど。と思った。いいじゃないか。このお店は。大変に良い。
そうして俺は、その日から毎晩のようにそのお店に通うようになったのだった。
キテレツ! バタフライさんのオカルト。
2年が経った。その頃になると俺はすっかりそのお店の常連になっていて、大体のお客さんの顔と名前を覚えていたし、覚えられていた。行けば誰かしら居るんで飽きない。バタフライさんも週に1度か2度ほどのペースで来ていてその度にコミュニケーションを取っていたけども、その段階でひとつ分かったことがあった。彼女はパチンコが大好きで、そして生粋のオカルターだった。
「バタフライさん、今日幾ら勝ったんですか?」
「今日? 15箱くらい」
「15箱……って何発くらいです?」
「15箱は15箱じゃァ……。玉とかなァ……」
彼女には「玉」という概念がない。常に箱計算である。普段パチンコをあんまり打たない俺は一箱に何発入るのかも知れない。その事を尋ねると、彼女は「こいつ分かってねぇなぁ」みたいな顔でこう言った。
「バッカお前! 箱は箱だろ!」
当時、ハタから見てても彼女がすげー勝ってるのは分かった。花の慶次と牙狼。そして北斗。毎日何かしらでブチ当てては豪遊を繰り返している。なんの仕事してるかサッパリ分からなかったけども、もしかしてパチプロなのかもしれない。
「すごいなぁ……。良く勝てるなぁ。コツとかあるんですか?」
「波だよ。波を読まないと勝てないゾ! パチンコは!」
「波……?」
「そうだよ。こうやって……あるじゃん上に行ったり下に行ったり……」
「あ、スランプグラフ?」
「そう! グラフ! な? ……読むんだよ」
「読む……っていうと……」
グラスを拭き上げながら、マスターがこういった。
「ひろしくん。ひろしくん。バタフライさん、大当りは店長が決めてると思ってるから」
「ああ……なるほど」
「バーッカお前ら。テメコノ! 入ってくんじゃねぇよ横から! テメコノ!」
「じゃあその、グラフを読むっていうと、例えばどういう……?」
「あのね、あそこの店あんじゃん。すぐそこの。あそこはァ、一杯出たら次の日、その後ろの、右斜めの台が出るんだよ」
「あー、回るって事?」
「いやぜんぜんぜんぜん。当るんだよ」
「あー……。ごめんなさい。ちょっと俺分かんねぇや……」
「お前パチンコ打たないからなぁ。説明してもさ、分かんないんだよなァ」
バタフライさんの珍言……いや、店舗攻略はそのほかにも山程ある。曰く「慶次は金玉(金保留)がハズレたらヤメのサイン」であるとか「一気に連チャンしたら暫く出ない」といったデジタル(?)なオカルトから、「裏にある台が当たってる時はその台は出ない」「玉が戻って入ると熱い」みたいな物理系オカルト。さらには「海を打つと運気が下がる」「整骨行ったら当たる」といった風水系オカルトまで。中でもインパクトが強かったのがコレだ。
「あのなー、パチンコはなー、回りすぎると良くないんだゾ」
この、ボーダー全否定の武力特化型オカルトだ。
「……何故?」
「ッたり前じゃん。テメコノ! ウチが店長だったら、回らない台を当てるし」
「ねーバタフライさん。店長はねぇ、決めてないのよ当たり……」
野暮だと思いつつ、つい正論を吐く。そして吐いてからしまったと思った。
「バッカテメコノ! テメバッカコノ! 分かってねぇなぁ……。ったくひろしって名前には禄な奴がいねェもん……。波決めてるの店長じゃん?」
「ンー……。その波ってグラフのことですよね?」
「そう。グラフ。店長が決めてるじゃんアレ」
「まー、広い意味ではそうなのかなァ……」
「じゃあほら、決めてンじゃん」
「決めてンのかなぁ……」
まあ、バタフライさんは確かに店長がボタン一個で当りを操作してると思ってるし交換率も知らないし出玉計算もボーダー理論も知らない。しかし、それで現実に勝ってる。頭でっかちで負けてるより、妙ちくりんな理解でも勝ってるのが偉いのは間違いないわけで。それ以上俺は何も言えなくなってしまった。
それに、だ。
バタフライさんの言う「店長との読み合い」というのは実は店舗攻略において最も大切な事だったりする。そういう意味では、バタフライさんのオカルトは大暴投ではあるものの結果的には正しい。なんせ彼女は負けて怒らない。次に活かそうと考える。鍵穴を押したら当たる! と信じてリーチ中にグイグイ押しまくり、ハズレたらプンスカ怒って台を叩くような人とは全然違うのである。冷静に捉えて「あ、そういえば3回転前に2つ同時に玉が入ったな。そういう時はハズレるんだ」と新たな発明をする。重要なのは、それで彼女が勝っているという事実だ。
この辺は、インドへの西回り航路を探してうっかりアメリカを発見したコロンブスに近い。彼は死ぬまでアメリカをインドだと思ってたし原住民をインディアンと呼び続けていたけども、それをしてバーカバーカとなじる人はいまい。歴史に残る偉業を為したという意味では正しく「発見した」のだから。
俺の人生にも大いなる影響が……!
バタフライさんは声がデカい。酔っ払った人間の声がデカくなるのは古今東西において普遍の現象だけども、彼女場合はそのデカさが尋常じゃない。
バーの常連に横チンくんという男がいる。彼には当時3歳の息子がいて、一時期極稀にバーに連れてきていた(東京都受動喫煙防止条例施行前)。それはそれは可愛いお子さんで、大変に人懐っこく。そして頭が良かったので常連たちの間での人気になった。俺もその子と会うと行き場のない父性が暴走して超デレデレになってたのだけども、そんな見ず知らずのオッサンに対しても、横チンの子はまばゆいばかりの笑顔を向けてくれていた。
ペプシコーラのオマケについていたボトルキャップ。セリエAの選手をモチーフにしたキャラがついてる。
「これはアンリ。こっちがロナウジーニョだよ」
「アンリ……ロナウジーニョ」
「そう。んでこの二人を……ピシュー……フインフインフイン……ドゥーン!」
「キャッキャッキャッ!」
「おお……コイツこれ好きだなぁ……。もっかいやる?」
「うん!」
「ピシュー……フインフインフイン……ドゥーン!」
「ドゥーン! キャッキャッキャッ!」
その日も「アンリとロナウジーニョのボトルキャップをゆっくり浮上させて空中で爆破するごっこ」で遊んでたのだけども、そこにバタフライさんがやってきた。俺の横で楽しく遊ぶ横チンJrに気づいてパッと顔を輝かす。
「おー! 来てまチュカ! 来てるんでチュカ! 何やってるんでチュカ!」
お道化ながらJrに近づくバタフライさん。すでに酔っ払ってるのか顔が赤い。彼女はJrの隣に座るとボトルキャップを手に取って何かやり始める。どうやらサッカーを教えてるらしい。が、当のバタフライさんもサッカーを知らず。気づけば九体のボトルキャップが円陣を組んで中央にライターがあるという、なんかクトゥルフ神話に出てくる邪悪な儀式みたいな格好になってた。当のJrはアンリとロナウジーニョのボトルキャップをゆっくり浮上させて空中で爆破するごっこがグイグイ来てるタイミングだったのを打ち切られたのがカンに触ったのか、スンとした無表情でまっすぐ遠くを見ていた。3歳児の表情じゃなかった。
「うわー、ほっぺぷにぷにでチュネェ! おモチみたいでチュネェ! うわ、やわらか~い!!」
チベットスナギツネみたいな表情の3歳児の頬を軽くつまんだり揉んだりするバタフライさん。やがてJrが口を開くや、信じられない言葉が耳に飛び込んできた。
「しゃわらないで!!」
触らないで。3歳児が本気でキレているのを俺は生まれて初めてみた。
「なんでなんでー! いいじゃん! ウチにほっぺ触らせろよ~! 食っちゃいたい! 食っちゃいたい!」
「……ンー! うるしゃーーい! しゃわらないで!!」
Jrが耳を塞いで首を振りながら拒否反応を示す。輝くような笑顔から一転。3分ほどの出来事だった。本人も多少はショックを受けているかと思ったら、2秒後には興味を無くしていたし、また横チンにJrの名前を100回くらい聴いては何かしらアカペラで歌っていた。
またこんな事もあった。
Hさんという非常に質の悪い酒乱のオッサンがいて、その人が出禁になる直前の事だ。どこで引っ掛けたのかフィリピン人の女性をお店に連れてきたことがある。類友理論でその女性もまた非常に酒癖が悪く、土足で店のカウンターに立って踊ろうとした。マスターに叱られて大人しくなったものの、それがカンに触ったのか二人は刺々しい態度を取るようになり、そこに居合わせたのが俺とバタフライさんだった。俺は平和を愛する土鳩のような男なので特に何もなかったのだけども、正義感が強いバタフライさんはその空気を察知してHさんに食って掛かった。やがて二人共立ち上がりフィジカルファイトの一歩前。これは流石にまずいと止めに入ろうとした所で、何故か彼女はHさんとフィリピン人女性に挟まれる形で席に座り、3人でなんか歌い始め、挙げ句に肩を組んだまま仲良く3人で椅子ごと後ろに倒れるという荒業をやってのけた。俺一体何を見せられているんだろうと思った。
その他、バタフライさんが怒りに任せて誰かに向けて投げたおしぼりが関係ない俺の顔面に命中したり。ビリー・ジョエルの『ストレンジャー』という曲がお店でかかる度「ウチこの曲若い頃メッチャ好きでずっと歌ってた!」と言いながら歌う歌詞がアルファベット1文字も合ってなかったり。あと、何故か人と人を妙にくっつけたがったり。
つい四年前の話だけども、俺は人生で何番目かに凹んでいた。二年半付き合った彼女と別れたばかりだったからだ。若い頃は女性と別れてもなんにも感じなかったものだけども、40を手前にしての離別は少々堪えた。だので酒に逃げる形でその店に入り浸ってたのだけども、そんな時、店に入るなりバタフライさんに声をかけられた。
「あー! 噂をすれば! ひろしじゃん。ひろし。どこ座るの? そっち?」
「ン? 何噂って。ハァ……。マスター。心の傷を癒やすレモンハイ下さい……」
「ウソでしょ。ビール?」
「うんビール……」
L字型のテーブルの長い辺。その両サイドに離れて座ってた俺とバタフライさんだったけども、彼女は他のお客さんの頭を越えて話しかけてきていた。結構離れていたけども、声はハッキリ聞こえた。なにせ彼女の声はデカんだもの。
「ひろし、この子知ってる?」
「ン? 誰……? あー……」
よく見ると、バタフライさんの隣には見知った顔がいた。何度か店で見かけたことがある。マイケル・ジャクソンファンの子だ。名前はたしか──。
「この子も彼氏と別れたばっかりなんだって。お前もだろ? じゃあもうお前ら──」
そういってバタフライさんは手をパンパンと二度叩いた。
「くっついちゃえよ!」
半ば強引に席を移動させられたその子が俺の隣に来た。なんかすいません。お互いにペコリと礼をする。
「ええと、ひろしです」
「知ってますよ。はるかです」
──ぱちんこにおけるオカルトというのは、結局のところスパイスだと思う。ハーブソルトがバジルソースを否定しても無意味なように、ガチの人がオカルターを否定する意味なんかゼロだ。重要なのは本人にとって美味しいかどうか。楽しいかどうか。勝ち負けとはまた別の次元に存在する話で、その次元というのは、実は勝ち負けより上位だと思う。なんせ、その日からきっかり1年後。入籍を済ませた我々がその店で開いたパーティで仲人を務めたのはバタフライさんで──……。
「ほらな。店のカウンターの端っこと端っこに座ってる男と女って、だいたいくっつくんだよ」
実のところ、彼女のオカルトは俺の人生も大きく変えのだもの。
INFOMATION
いいね!する
3668関連記事
ランキング
24時間
週間
月間





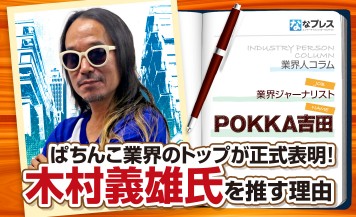











この記事にコメントする