ギャンブルはセーフでもおっパブはアウト!学生時代のあしのが東大卒准教授に初代ミリオンゴッドを打ってもらった話
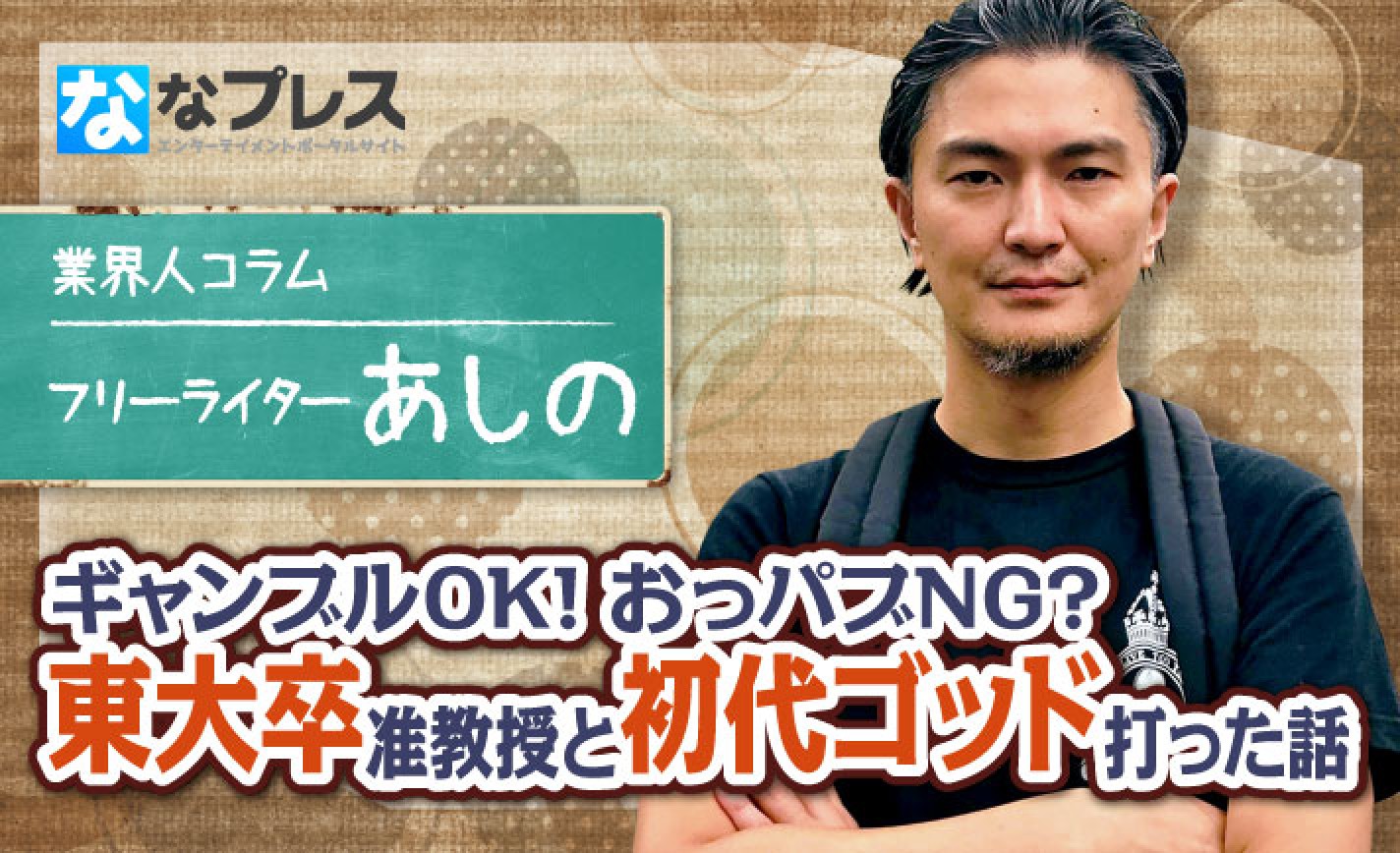
もはやこのご時世、学歴で人を判断するのはナンセンス極まりない話だけども、やっぱり「東大」というパワーワードはその人の価値をブチ上げる最強のカードだと思う。
例えば先日浅草の立ち飲み屋で知り合ったオッサンは鼻毛がイソギンチャク並に出ていた。ベロンベロンに酔っ払ってめっちゃ話しかけてくるんで面白くなって相手してたけど、なんかの拍子でその人が畜産関係の研究者で東大卒である事が判明した瞬間、俺は敬語になった。それまでは「おいちゃん」と呼んでたけど、一瞬で「先生」になった。鼻毛までもがなんだか知的に見えてくる始末。
あと、以前つくばエクスプレス線に乗ってる時に目の前にネルシャツ着てる学生がいた。ラップトップを膝の上に乗せてなんかやってる。俺は「ああこの子はつくばから秋葉に向かってて、恐らくPCでエロゲーかなんかやってんだろう」とそう判断した。オイオイ車内でエロゲーは無いぜ少年。自重したまえよ。と。でも目を凝らしてみるとPCの背面にテプラで「東京大学工学部」って書いてあるのを発見するにつけ、俺は自分をぶん殴りたくなった。これから日本を背負う青年になんという不遜。あの画面にはきっと何か良く分からん計算式とかが表示されておるのだろう。ネルシャツも逆にシャレオツ。時代に左右されぬ揺るぎなき信念みたいなのすら感じたものである。
よしいこう。今回はそんな話だ。いくぜプレス!
地方のFラン大学での話。
2002年。当時俺はまだ大学3年生だった。1979年生まれでまだその時分に大学生というのは全然計算があってないけども、要するに浪人したり休学したりでそうなっていた。美術史というちょっと特殊なゼミを取っていて、図像学とかを学んでいた。博物館や美術館に行くと専門の職員がいてその展示品の管理や案内なんかをしてくれるけども、あれを学芸員という。今はキュレーターという呼び方をするのだけども、その資格を取る為に必要な単位を満たすためになんだかんだそうなった感じだ。
とはいえ当時俺はパチスロにドハマリしていてほぼ学校へは通っておらず、ただいたずらに日々を浪費──いつしか「学芸員って面白そうだな」というぼんやりした目標も消え、最終的には「せめて教員免許だけでも取って卒業しよう」みたいな駄目学生にありがちな軌道修正を余儀なくされていた。
教員免許を取るのにはちょっと面倒な単位をいくつかこなす必要があった。代表的な所で言うと「教育学」「児童心理」あたりがそれだ。当然担当科目の概論も取っておかないといかんので「地誌」やら「法律学」「日本史」「世界史」が加わる。厄介な事に大半が卒業に関係ない単位だった。つまり純粋に授業時間が増えるだけ。しかも俺はただ免許が欲しいだけで教員になるつもりはゼロだったので、必定、授業中はスロマガばっかり読んで過ごしていたものだ。
さて。そんな生活の中。とある学科の准教授と出会った。まだ若い先生で、20代後半──。ぽっちゃり系というか、ちょっと太ってて、そして若ハゲが来ていた。彼の名前をS先生という。最初は見た目が面白かったので仲良くしてたけども、話してみるとさらに気に入った。びっくりするくらい純粋なのだ。タバコも吸わない。酒も飲まない。運転免許もない。おまけに本人曰く童貞だとの事。王道からドロップアウトした駄目学生にとっては格好の遊び相手に思えた。仲の良い友人と何人かで講義の合間に研究室に通ううち、いつしか我々はプライベートでもガッツリ遊ぶ間柄になった。
──親睦を深める中でひとつ判明した事実がある。そう。彼は「東京大学院卒」だった。
20代で准教授になってるんだからそりゃそうなんだろうなと妙に納得したのを覚えているが、一方でその純粋さに膝を打つ思いがした。なるほどねと。だってもう、俺と彼では人生の中で「勉強」につぎ込んだ時間が天と地ほどに違う。彼の前では俺がやってきた勉強なんぞ坊主の手習い未満。なんせ彼は若くしてすでにハゲかけている。これだってナチュラル・ボーン・ハゲではないはず。後天的なものだ。そう。毛根に影響が出るくらい学びに学んできたのである。
事実、彼は俺や友人が教えた事を超スピードで学んでいった。まず酒。そしてタバコ。次にスラッシュメタル。勧められるがままに自動車免許も取得。車を買う頃には俺より車種に詳しくなっていた。さらに、だれが教えたのか知らんが「モーニング娘。」にもすぐハマり、速攻でメンバー全員の名前と生年月日を暗誦できるようになった。まるで海綿である。スポンジだ。全部学ぶ。そしてこなす。そしてハゲてゆく。
ある時俺は思った。この人パチスロ教えたらハマるんじゃなかろうか。と。
尊敬すればこそ何かしらんが笑える。
初代「ミリオンゴッド」が発売されて少し経った頃だ。当時俺はおみくじ感覚で「1日千円だけ必ずミリゴを打つ」というのを日課にしていた。まあ当たり前だけど全然当たらない。その日も着座してサンドに千円札をぶち込むや黙々とノルマをこなす気持ちで打ってたのだけど、なんか知らんが聞いたことがない音がして画面に押し順ナビが表示されていた。うそん、と思った。一瞬意味が分からなかったけど、どうやらSGGをブチ当てたらしい。1/4096である。バクバクと高鳴る心臓。震える手で消化してるとさらにSGGがもう一つ。これは流石に尻が浮いた。その後もなんだか良く分からんまま連チャンが続きあれよあれよと言う間に積み上がるドル箱。そして、いよいよ万枚までの折返しを越えるか越えないかくらいの所で尻のポケットにねじ込んだケータイが震えた。
表示画面を確認する。大学の友達からだ。S先生と一緒に晩飯を食いに行かないか? との事。それどころじゃないのよねと思ったけども、ふと「ああ、これS先生に消化してもらおう」と思った。なんでそう思ったのかよく分からんが、当時の俺にはピカイチで素敵なアイデアに思えたのだ。
(今、大学の近所の店でミリゴ打ってるんだけども、5000枚くらい出てる)
(マジで? 晩飯奢ってよ)
(いいよ。もうちょいかかるからS先生も連れてきてよ)
(分かった。店どこ?)
10分ほどすると、友人が店内に姿を表した。俺の椅子の後ろにドスンと置かれた万両箱を見て爆笑する。すげえすげえと手を叩く。親指を立てフフンと笑顔を返す俺。
「先生は?」
「車で待ってるよ」
「ちょっとさ、これ先生に消化してもらいたいんだけど」
「え、なんで」
「いや、面白そうじゃない?」
「えー、打つかな……?」
「先生がここ座ってんの見たくない? 笑えると思うよ」
「まあ……。ちょっと面白そうだけども……。じゃあ一応連れてこようか」
「うん。よろしく。まだたぶん続くから」
「分かった──」
しばらくして、友人が先生を連れてきた。初めて入るホールに面食らったのか。あるいはミリゴの島の熱気にあてられたのか。少し落ち着かない様子だった。
「あしのちゃん、なにこれ……。こんな雰囲気なんだパチンコ屋さん……」
「凄いでしょう! めっちゃ面白いんですよコレ。先生、ちょっと座ってみて下さい。ここ……」
「え。俺が打つの? 嫌だよォ! 怖いよ何か」
「いやー! 大丈夫! 何事も経験ですよ。経験──!」
「えー……。マジで言ってるのそれ……。あー……。じゃあちょっとだけ……」
席を交代して後ろに立つ。普段マイクを片手に「パノプティコン」や「ヨハン・ホイジンガ」について熱弁を振るう先生がAT中のミリゴに座ってるだけで既に笑えた。
「先生、そこ。そのボタン押して、レバーを叩くんです──!」
「え、何、聞こえない。全然無理。どうやんの。これ? こう?」
「そう! で今なんか数字出てるじゃないですか。これ順番に押すの」
「これでいいの? これ押すの? これ?」
「そう!」
「次これ?」
「そう!」
「で、これ?」
「そうそう!」
「うわ何かメダル一杯でてきた! 無理!」
「無理じゃない無理じゃない! まだホラ、あと30Gくらいありますよ!」
「マジで。これ辞めようよあしのちゃん。怖いよ何か」
「怖くない!」
腹を抱えて爆笑する俺と友人。状況も絵面も何もかもがツボだった。今思えば俺は先生の事をかなり尊敬していた。大人と子どもの境界上。社会人と学生の間。当時の俺はマージナル・マンであり、そしてモラトリアムだった。目上の者は全員敵だくらいに思っていたし、自分自身すら何者かを規定できていなかった。そんな中で、先生はほぼ唯一といっていいほど腹を割って話せる大人だった。自分の味方をしてくれる、賢くて頼れる大人だったのだ。それがテンパりながらゴッドゲームを消化している。
「ああ、何も出ない。ねぇあしのちゃん、数字何も出ない。これは……?」
「あ、これ普通に押してください」
「普通……?」
「ええと、左から順番に──」
「普通が左からなのね? 数字出るのは普通じゃないのね?」
「そうです! ほら、もうちょっとで終わりです。ここの数字がゼロになったらATが終わりなんで」
「ATっていうのは何なの?」
「アシスト・タイムの略で、数字が出る状態の事です。押し順っていうんですけども。それが出てる状態がアシストなんですよ。普通出ないんでその黄色い7が揃わないんですけども、今はアシストされてる状態だから7が揃ってメダルが出てくるわけですよ」
「普通の状態っていうのは何?」
「普通の状態っていうのは──。あれ先生いま勉強してます?」
「そりゃそうだよ! 知らない事だからさ!」
「マジか……。普通っていうのはホント、普通の状態です。いまは普通じゃなくて、大当たり中なんですよ」
「ATっていうのが大当たりなのね?」
「そうです。その通り」
「じゃあ、もうすぐ大当たりが終わるっていうこと?」
「そうです!」
やがて画面が暗転。ゴッドゲーム終了である。ここからは継続の当落を通知する5ゲームのG-zoneである。
「なにこれ。どういうこと?」
「これは……。何ていうんだろう。5回転中に、なんかこの……数字が揃ったらデデーンっつってまた大当たりです」
「デデーンっていうのは?」
「ええと、効果音です」
「ああ……。そうか。これはATじゃないのね?」
「これは違います」
「じゃあ順押しでいいんだ……」
「──吸収早いな!?」
1G目。2G目。3G目。テンパイするといちいちこちらの様子を確認してくる先生の様子を微笑ましく見ながら、俺はドンと構えていた。大丈夫。計算上まだ継続する筈だ。敢えてそれは教えずに迎えた5G目。画面上に奇数絵柄が揃っていた。
「うわ揃った! 怖いなこれ。なんか怖いよ──!」
先生の生涯初のパチスロはミリオンゴッド。ゴッドゲーム中からスタートし2セット消化して終了だった。
次は夜の街のお勉強へ。
大学に車を置いてタクシーに乗り、20分ほど離れた居酒屋へ来ていた。学生が良く使う安い店だったけど、その日はさらに俺がすべての代金を持つ事になっていたので、友人も先生も大変に良く食べ、そして飲んだ。
「いやー、パチスロって怖いねぇ!」
「怖くはないでしょう別に。え、怖かったですか?」
「怖いよやっぱ。雰囲気が」
「あー……。雰囲気かァ……。まあそれはあるかも」
ビールを飲みながらタバコを吸う先生。つい最近まで肺まで入れずにフカすポーズだけの喫煙だったが、近年はすっかり様になってきている。
「パチスロってやっぱ、嫌でした? 先生」
「嫌じゃないけど、あんまり良くないかなっていうのは思うよ」
「良くないというのは、どこからですかね。倫理とか道徳とか──」
「それと、一般的には宗教も絡むよね。ボク個人は深く考えた事が無かったから、単純に生理的な嫌悪感かもしれない。まあ『ホモ・ルーデンス』の中ではアレア──『偶然の遊び』もしっかり定義されて類型化されてるんだし、お金のやりとりを抜きにして考えればパチスロっていうのは全然アリなのかもしれないね」
「それはつまり……。まあいい経験になったと」
「なったね。それは間違いない」
「今後やります?」
「どうだろう。なんとも言えない。やらないともやるとも──」
煙を吐き出し笑う先生。俺も思わず笑顔になった。ちょっとホッとしたのもある。尊敬する先生が、パチスロを嫌わなかった。それだけで充分だ。そのまま友人と先生、3人で酒を飲んで日付が変わるくらいの時間まで店にいた。支払いを終える。安居酒屋だけあってたっぷり腹を満たしても一万円くらいのものだった。ポッケにはまだ神が与え給うた軍資金がたんまりある。こっそり友人に耳打ちする俺。友人が悪い顔で頷く。
「先生、ちょっとこれから遊びに行きませんか。面白い店があるんで」
「ん。何の店?」
「お酒飲む所です」
「ああ、いいね。いこうか」
裏路地に突入する。客引きたちを交わしながらいくつか角を曲がる。雑居ビルの非常階段を登り、ユーロビートのリズムが漏れ聞こえる扉の前になった。
「……なんだいここ」
「おっパブです」
「おっパブ?」
「おっぱいパブ。ランジェリー・パブですね」
「ランパブ!」
「そうです」
ドゥン! ドゥン! ドゥン! 低音のリズム。扉が開いて黒服が出てきた。
「何名様ですか?」
「3人です」
言うが早いか、先生が手を挙げた。
「あ、僕無理!」
「え……?」
「いいよぉ僕は。そういうのいいよぉ。無理無理。駄目だって。流石に駄目」
「ただのおっパブですよ?」
「ンー。だっておっぱいでしょう?」
「おっぱいですねぇ」
「いやー……。駄目かなぁ。ごめんあしのちゃん。帰る! 無理!」
「あ、先生ちょっと──」
また明日ね! と言いながら、有無を言わさぬ様子でタクシーに乗り込む先生。車が角を曲がって見えなくなるまで見送ってから、呻った。友達と目が合う。
「駄目だったか……」
「駄目だったねぇ……。もうちょっとだった」
とぼとぼと再び非常階段を登ってお店に入店する我々。やがて目の前に現れた嬢のおっぱいを揉みながら思った。ギャンブルはギリギリオーケー。おっぱいはNG。その間に横たわる溝には何が詰まってるんだろう。道徳か。倫理か。宗教か。ジェンダーかも。死生学だったりして。ミラーボールが回る。マイクパフォーマンスが始まった。大回転。サービスタイムだ。出勤している嬢が入れ代わり立ち代わり横に座ったり膝に座ったりする。おおきいおっぱい。ちいさいおっぱい。いろんなおっぱいを見ているうちに、一つ悟った。
まあこれ傍から見ればすごい間抜けなシーンだから、単純に生徒には見せられんよね。で、こうなるのが分かってるってことは、ははぁん。
奴さん、もう既に経験済みなんだね。と。
INFOMATION
いいね!する
356関連記事
ランキング
24時間
週間
月間

















この記事にコメントする